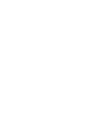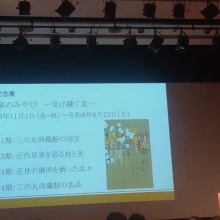※ ※ ※
“猪木イズム”とは何なのか。ある者は「ストロングスタイル」のことだと言い、また、ある者は「いつ何時、誰の挑戦でも受ける」という精神だと言う。その一方で「アメリカンプロレスの亜流にすぎない」と、猪木イズムの存在自体を完全否定する者もいる。
猪木自身が現役時代から今に至るまで、プロレスラーのあるべき姿として主張しているのは、第一に「強くあらねばならない」という点である。
力道山の時代からプロレスというジャンルは八百長と侮蔑され、各種のスポーツよりも格下と見なされてきた。そんな評価を覆すためにも、猪木にとって“強さ”は必須のものだった。
猪木は自らの強さを証明するため、格闘技の頂点であるプロボクシングのヘビー級王者、モハメド・アリにも戦いを挑んだ。アリと同じリングに上がり、できることならこれを凌駕することで、プロレスラーの強さを証明しようとしたのだ。
ただし、猪木が目指したのは自己満足的な強さではない。強さと同時に、名誉やビジネス的な成功も追いかけた。リアルな強さを追求しながら、ショービジネスとしても成功させる。この矛盾するようなテーマを両立させる闘いを、猪木は“格闘芸術”と称した。
“世界一の男=アリと闘った猪木がやるのだから、タイガー・ジェット・シンとの血みどろの抗争であろうと、国際軍団との1対3変則マッチであろうと、マサ斎藤との巌流島決戦であろうと、決して茶番などとは言わせない”というのが、その理屈である。
そして、実際にこれが受け入れられたことで、70年代後半から80年代にかけての新日本プロレスブームが起こり、多くの猪木信者が生まれることとなった。
また、猪木はいわゆるアングルにおいてもリアルさを求めた。
猪木と新日が絡んだプロレス史上に残る“事件”には、シンの伊勢丹前襲撃事件や第1回IWGP決勝戦での失神KO負け(優勝はハルク・ホーガン)、猪木自身の引退後にも、愛弟子である小川直也vs橋本真也の不穏試合といったように、いまだ真相が明らかになっていない事例が多々ある。
これらについては関係者の話もまちまちで、猪木も深く語ることはない。そのため想像に頼らざるを得ないのだが、つまりはプロレス的なストーリーとは一線を画す事件を猪木が望んだ結果ではなかったか。
プロレスに興味のない一般社会を振り向かせるには、プロレス内でしか通じない抗争ではなく、一般紙にも記事として掲載されるリアルな事件を起こすしかない。
そのためには警察沙汰になろうが、一つの大会がメチャクチャになろうが、小さなことにすぎない。尋常ではない猪木の強烈な意志によって、プロレス的な文脈では理解が及ばぬ事態が引き起こされたのである。
★社長を解任されいら立ちが爆発
さらに、猪木は試合においても、時にリアルな感情をむき出しにした。
1983年8月28日、欠場明けの猪木は東京・田園コロシアムでラッシャー木村と対戦。卍固めで快勝して見事に復帰を飾ったのだが、シリーズ後半の9月21日、大阪府立体育館で再度組まれた同一カードは、異様な結末を迎えることになる。
試合開始から間もなく、唐突に怒りをあらわにした猪木は、木村に殴りかかって場外に落とすや、容赦なく顔面を蹴りつける。これに大流血した木村だが、猪木による殴る蹴るのリンチまがいの攻撃はやむことがなく、わずか5分ほどで木村を血の海に沈めてしまった。
一連の国際軍団との抗争を無にする一方的な試合ぶりで、敗れた木村は悔しさからか泣いているようにも見えた。さて、この試合の裏には何があったのか。
復帰戦の数日前、猪木はアントン・ハイセル事業への過剰な投資の責任を取らされ、新日社長の座を追われていた。復帰戦で勝利した後、マイクで「俺の首をかき切ってみろ!」とアピールしたのは、その怒りのままの叫びであった。
社長解任に伴いマッチメーク権も選手会に移譲され、木村との再戦はその選手会による要求だった。だが、勝ったばかりの木村との再戦に納得できない猪木は、「こんな試合を組んだおまえらのせいだ」とばかり、わがまま勝手な振る舞いに出て、ライバルだったはずの木村を叩き潰してしまったのである。
リングの内外を問わず、虚実の間を行き来する。そんなレスラーは、古今東西を見渡しても猪木をおいて他になく、それこそが猪木イズムの核心と言えるのではないだろうか。
アントニオ猪木
**************************************
PROFILE●1943年2月20日生まれ。神奈川県横浜市出身。身長191㎝、体重110㎏。
得意技/卍固め、延髄斬り、ジャーマン・スープレックス・ホールド。
文・脇本深八(元スポーツ紙記者)