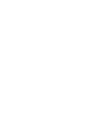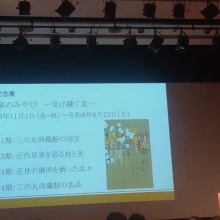ところが、近代的な輸送艦艇を持たない日本海軍は1942年後半のガダルカナル島をめぐる攻防戦において、敵制空権下の輸送作戦に貴重な駆逐艦や巡洋艦を投入せざるをえなくなり、艦隊戦力に少なからぬ被害を出した。そのため、海軍軍令部は、ガダルカナル島を放棄した後の1943年になって、敵性海域を強行突破して陸上部隊を揚陸可能な高速輸送船の開発を決意したのである。この高速輸送船が一等輸送艦であり、福井静夫氏の著作によると開発の経緯には相当の紆余曲折があるようだが、残念ながらその具体的な内容については判然としない。
まず、海軍軍令部は開発に先立って1943年に設計を完了した丁型駆逐艦(松などの簡易量産型駆逐艦)の主機を減らし、その空きスペースに物資を搭載する艦を計画した。しかし、その計画ではあまりにも効率が悪いと判断され、呉工厰の技術者を中心とした作業チームが新たに設計することとなった。実際、呉工厰の作業チームは基本計画に関する部分まで含めた大きな裁量権を与えられ、上陸用舟艇の進水装置などの特殊装置等は実物大模型を制作して開発している。
1943年秋には最終的な設計案がまとまり、翌年には第一号艦が竣工した。その後、敗戦までに46隻の建造が計画されたが、実際に完成したのは21隻に留まっている。また1944年に日本海軍が輸送艦との艦艇種別を設けるまで、一等輸送艦は特務艦特型の略である「特々」と呼ばれていた。
一等輸送艦は260トンの各種物資を搭載可能で、また4隻までの上陸用舟艇、または水陸両用戦車を搭載しており、船尾にはスロープが設けられていて、クレーンを使用することなく物資を搭載したままの舟艇を発進させることができた。加えて強力な対空、対潜兵装も備えており、護衛艦として運用することもできた。実際、ソナーや水中聴音機の他、レーダーも備えていた艦があったようで、輸送と護衛の両方をこなす万能艦として重宝されている。最大速力は22ノットで、巡航速力も18ノットに達しており、速度性能は高速商船の五割増しだった。
その他、一等輸送艦は甲標的や回天といった超小型潜水艇の搭載も可能であり、1944年の試験で洋上から発進させることも可能なことが明らかとなった。そこで、陸上部隊や補給物資以外にも超小型潜水艇の輸送を行っているが、前線で母艦として作戦行動を行った事例はないとされている。また、船尾のスロープを活かして、臨時敷設艦として作戦に従事した艦もあり、その活用範囲は驚くほど広範囲に渡っている。
前述のように一等輸送艦は非常に使い勝手のよい万能艦であり、また前線もこの種の艦艇を切実に必要としていたため、竣工した端から前線に投入された。ブロック工法を採用して量産を最優先した設計となっており、材料さえそろっていれば五週間でほぼ竣工状態まで工程を進めることができた。しかし、当時の戦局は極めて逼迫しており、敗戦までに21隻が竣工したものの、数か月以内に16隻が戦没している。
また、敗戦時に航行可能だった5隻の内、復員輸送中に事故で失われた二十号輸送艦を除く4隻は戦後に改装され、短期間ながら小笠原方面で捕鯨母船として操業しており、最初で最後の「クジラを捕った帝国海軍艦艇」となった。柴達彦著「鯨一代」によると、最初の出港時にはマストに漁業会社の社旗と軍艦旗を掲揚し、日新丸行進曲(捕鯨船のテーマ曲)や軍艦マーチを高らかに流していたようだ。また、同書によれば連合軍は漁業会社に提示した貸出艦艇リストの筆頭は戦艦長門だったそうで、実現可能性はともかく興味深いエピソードであろう。
一等輸送艦はいかにも日本海軍が好みそうな万能艦で、しかも捕鯨までこなせるマルチプレーヤーでありながら、そこそこの戦力価値を持っていたという意味で非常に珍しい存在である。輸送艦という艦種分類が災いしてか、いささか兵器としての注目度が低いように思われるが、もう少し評価されてもよい艦艇であろう。しかし、例え兵器としての性能が少々優れていたとしても、登場した時期がいささか遅く、また数も少なすぎたと言わざるをえないのだ。 (隔週日曜日に掲載)
■「一等輸送艦」データ
基準排水量1,500トン 長さ89.00メートル 幅10.20メートル 主機・軸数艦本式オール・ギヤード蒸気タービン・1軸1基 主缶ホ号艦本式水管缶(重油混焼)2基 出力9,500馬力 速力22.0ノット 兵装12.7センチ連装高角砲1基、25ミリ三連装砲機銃3基、25ミリ連装砲機銃1基、25ミリ単装砲機銃4基、爆雷18個 搭載量260トン及び14メートル特型運貨船(通称大発)4隻