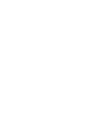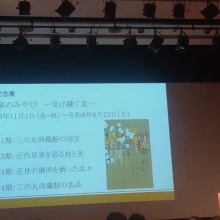しかしながら、どこか物足りなく感じる昭和ファンもいるのではなかろうか。
※ ※ ※
90年代半ばからの新日本プロレスファンに「最強の外国人は誰か?」と尋ねれば、その多くから「スコット・ノートン」の名前が挙がるだろう。
昭和の時代からのファンにしてみれば、「アンドレ・ザ・ジャイアントやスタン・ハンセン、ハルク・ホーガン、ビッグバン・ベイダーらを差し置いて、なぜノートン?」と違和感を抱くかもしれない。
しかし、1990年の初来日から10年以上にわたってトップ外国人の座を守り続け、100回以上来日したことへの敬意も含めて、当時のファンにとってはノートンが大きな存在であったことに違いはない。
元アームレスリング世界王者で、映画『オーバー・ザ・トップ』では端役ではあるがシルベスター・スタローンとも共演、プリンスのコンサートツアーではボディガードを務めたという。輝かしいながらも、同時にどこかうさん臭さも漂う肩書を引っ提げて来日したノートン。
アームレスリングに限らずボディビルや重量挙げ王者と聞くと、長州力と異種格闘技戦を行ったトム・マギーのような“食わせ者”ではないかと、うがった見方をしてしまうのは昭和ファンの習い性であろう。
「しかし、ノートンはマサ斎藤のブッキングによる来日で、これはベイダーと同様。マサ自らレスリングの手ほどきをしたようで、基礎がしっかりできていました」(プロレスライター)
’92年にはトニー・ホームとのコンビでスタイナー・ブラザーズを破り、IWGPタッグ王座を獲得。翌年にもヘラクレス・ヘルナンデスとの「ジュラシック・パワーズ」でヘルレイザーズを破り、2度目の戴冠をするなど存在感を発揮した。この頃から新日においては、“ノートン超え”がトップに立つための合言葉となっていった。
「日本マットで順調に成長していったノートンでしたが、nWoジャパンに加入したことは、果たしてノートンにとっては、どうだったのか」(同)
NWOジャパンの主役はあくまでも蝶野正洋であり、ノートンはその引き立て役に回る格好となった。これは後に、やはり蝶野が立ち上げたブラック・ニュー・ジャパンの頃まで続くことになる。
岩山のようなゴツい体躯から溢れ出すパワー、フライング・ショルダーアタックなどに見る素軽い動き、一流の素材であることは多くが認めるところでありながら、かつての大物外国人たちのような伝説的名勝負に恵まれなかったのも、こうした経歴によるところが大きかった。
★IWGP戴冠も会社の事情含み
新日トップの証しであるIWGP王座も2度獲得しているが、最初は蝶野が負傷して返上したとき、まだ海外武者修行帰りの若手だった永田裕志を破って獲得したもの。いわば蝶野の代役である。
2度目は佐々木健介から藤田和之へタイトル移動するためで、このときは“つなぎ”のような扱いだった。
「アントニオ猪木の意向で、弟子の藤田を王者にするのが既定路線でしたが、当時の現場監督だった長州は、自分の子飼いの健介が直接対決で藤田に負けることを嫌がった。それで間にノートンを挟んだというのが、大方のプロレスファンの見解でした」(同)
そんな状況下でのIWGP戴冠であっただけに、ノートンが勝った内容よりも、敗戦後の健介が藤田に対して放った「正直すまんかった」のマイクで知られる試合となってしまった。
のちにノートンは、「新日からのオファーは一度も断ったことがなかった」と語っている。
デビュー間もない頃からトップ扱いしてくれた新日への恩義があり、人としては正しい考え方なのだろうが、そうした便利屋的なところが強烈なインパクトを残せなかった要因と言えなくもない。
もっとも平成以降は、プロレスにおいてもコンプライアンスを求める傾向が強まり、猪木の無法ぶりなどはむしろファンに敬遠され、時には非難の対象になるぐらいなので、ノートンの従順さというのはそんな時代に合ったものだったのかもしれない。
’89年のデビューから30年がすぎた今も、ノートンは正式に引退表明していない。アメリカの自動車販売会社に勤める傍ら、ときおり日本にもやってきてTEAM2000の再結成などに参加している。このあくせくしない感じも、どこかノートンらしいと言える。
スコット・ノートン
***************************************
PROFILE●1961年6月15日生まれ。アメリカ合衆国ミネソタ州ミネアポリス出身。
身長190㎝、体重150㎏。得意技/ジュラシック・ボム、パワースラム。
文・脇本深八(元スポーツ紙記者)