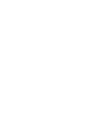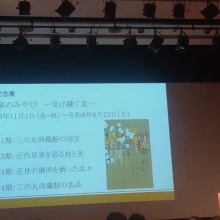かつてアントニオ猪木は「プロレスに市民権を」と熱く語っていた。一部のプロレスファンだけが熱中するものではなく、広く一般からその価値を認められたいという意味である。
ひるがえって令和のプロレス界を見てみると、会場には若い女性が集まり、テレビのバラエティー番組ではレスラーたちが人気タレントと並んで出演している。こうした状況をもって「市民権を得た」とも言えそうだが、では、これが猪木の望んだプロレス界の理想なのか? おそらく「決してそうではない」と昭和のファンは反発するだろう。
★プロレスファンが抱く選民思想
新日本プロレスの旗揚げ当初に掲げた“キング・オブ・スポーツ”の言葉通り、プロレスがあらゆるスポーツの頂点に立ち、万人から尊敬を集めるような存在になることこそが、猪木の悲願でありロマンであった。
だが、当時は他のスポーツやエンターテインメントと同列どころか、「ずっと価値の低いもの」とする声が主流だったために、まずは“市民権”という言葉を使ったのである。
世間から低く見られた理由とは、言うまでもなく八百長の問題であった。
「なぜ、ロープに振った相手が戻ってくるのか」「相手の攻撃をあえて受けるのはなぜか」「そもそも勝敗は最初から決まっているのではないか」といった批判や疑問は、力道山の時代から幾度となく繰り返されてきたが、プロレス側から明確な回答がなされることはなかった。
世間的には「厳格なルールが定められ、それにのっとって真剣に行われる」のが、まっとうな競技であると理解されている。そうした価値基準からすれば、反則が当たり前でパフォーマンスも過剰、余計なものが盛られまくったプロレスは、まったくもって「くだらない」ということになる。
これに対して、のちの直木賞作家である村松友視は、デビュー作となった『私、プロレスの味方です』において「余計なものがあるから素晴らしいのだ」との視点を提示した。
決まり事や常識を超えたところに人間性の発露があり、そこに感動が生まれるというプロレスの捉え方は、それまで世間一般からはもちろんのこと、家族や友人からも「プロレスなんてくだらない」とさげすまれてきたファンにとって、大きな心の支えとなった。
しかし、その言説は平易な文章とは裏腹に、芸術論的な小難しい理屈を多分に含んだものであり、これをアンチの人々が積極的に受け入れたわけではない。そのため、熱心なファンたちは「分かる者だけ分かればいい」「プロレスを楽しめる我々こそが高尚で、分からない世間は低俗」というような一種の選民思想を抱くようになった。
★大きな反発を生んだ新路線
プロレスファンのマニア化が進む中、別のアプローチでメジャー化を図ろうとしたのが、1987年4月に放送開始した『ギブUPまで待てない!! ワールドプロレスリング』であった。
当時、好感度ナンバーワンの山田邦子をMCに迎えて、それまでのプロレス中継『ワールドプロレスリング』を“プロレス+バラエティー”の名のもとにリニューアル。しかし、この方針は“選民”であるプロレスファンに受け入れられず、むしろ「何も知らない奴らがプロレスを玩具にしている」と大きな反感を買うことになる。
それを象徴したのが、海外遠征中に途中帰国し、同番組に出演した馳浩である。山田の「血なんかはすぐに止まるものなんですか?」との質問に、「つまらない話を聞くなよ!」と語気強く応じ、さらに馳は「止まるわけないだろう!」と続けた。これを受けて萎縮する山田…。
まだ若手にすぎなかった馳が、当代きっての人気タレントに堂々と反論してその軽口を封じたことに、ファンはこぞって喝采を送ることとなった。プロレス界を取り巻く空気を見事にすくい上げた、万事配慮の行き届いた馳ならではの名言であったが、一方で「やはりレスラーは乱暴で口の利き方を知らない」との批判も起こったという。
結局、テコ入れは大失敗に終わり、テレビ朝日はバラエティー路線から撤退。『ギブUP〜』はわずか半年で終了して元の『ワールドプロレスリング』に戻ったものの、悪循環から視聴率は振るわず、その後のプロレス中継は夕方枠、さらには深夜枠へと追いやられることになる。
馳浩
***************************************
PROFILE●1961年5月5日生まれ。富山県小矢部市出身。身長183㎝、体重105㎏。
得意技/ノーザンライト・スープレックス、裏投げ、ジャイアント・スイング。
文・脇本深八