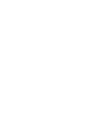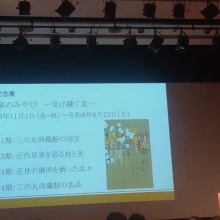印象深いだけでなく、世代交代の第一歩を告げる歴史的名言であった。
※ ※ ※
スタン・ハンセンの言葉の前提として、まず、当時のテリー・ファンクが置かれていた状況を押さえておく必要がある。
テリーは1980年(昭和55年)、主に膝の具合が悪化したことを理由として「3年後の誕生日に引退」を表明していた。実際問題として長年の激闘により、膝だけでなく体のあちこちが傷んでいた。
それでも引退までに3年という長めの期間設定をしたのは、その間の全日本プロレスと、試合を中継する日本テレビのビジネスを考慮したからであろう。
’77年の世界オープンタッグ選手権に端を発したアブドーラ・ザ・ブッチャーとの抗争は、ブッチャーが割れたビール瓶でテリーの胸を突き刺すという、テレビ放送不可の状況にまで至ってしまった。そのため“テリー引退”というアングルを用意することで、新たな展開を期したという部分もあったに違いない。
★入場時に発する雄たけびの意味
ところが’81年、引退までの抗争相手となるはずだったブッチャーが、新日本プロレスに引き抜かれてしまう。それでもテリーの引退期日はすでに設定されていたため、何かしらのストーリーをつくり出さなければならない。そこに登場したのがハンセンだった。
新日からハンセンを引き抜いた直接の当事者はテリーである。言うなればテリー自らが、引退ロードのライバルとしてハンセンを指名したわけで、それにハンセンが応じたのが掲出の言葉である。
さかのぼって’72年頃、ハンセンがNFLを解雇されて中学校の教師を務めていたとき、プロレスにスカウトしたのもテリーであった。そこからテキサス州アマリロの“ファンク道場”において、ハンセンはジャンボ鶴田やボブ・バックランドらとともに、プロレスの基礎を学びデビューを果たしている。
このようにハンセンにとってテリーは、プロレス界においての師匠であり、最大の恩人であって、それに対して遠慮会釈なく牙をむくというのは、その後、全日一筋で尽くしたハンセンの義理堅さからしても考えにくい。
この「テキサスの化石になれ!」というのが、ハンセン自ら考え出したものなのか、全日なりテリーなりが用意したものなのか、はたまた報道陣の創作物なのかは定かではないが、いずれにしてもテリー引退というストーリーの中のワンピースであった。
ところが、話がそこで収まらないのがプロレスの面白いところである。
新日時代からお決まりになっていたハンセン入場時の雄たけびは、実況アナもファンも「ウィー」と叫んでいると思っていたが、実のところ「ユース!」であったということは、後年になってハンセン自らが明かしている。ユース=若い、若者。「俺は若い」「年寄り連中には負けない」という思いは、早い時期からハンセンが抱いていたものであった。
つまりハンセンは、長州力や前田日明がアントニオ猪木に迫ったよりもずっと前から、1人で世代抗争を仕掛けていたわけで、引退後には「トップチームのポジションを得るためにはリアルな競争に挑むしかなかった」とも語っている。
★日本マット界の世代交代を実現
そうした信条に基づいた暴走ファイトは、テリー引退ロードにおいても爆発する。’81年、世界最強タッグ決定リーグ戦での突然の乱入から、いったんはジャイアント馬場との抗争に踏み込んだハンセンだったが、これがひと段落するとテリーに照準を合わせる。
’82年の同大会にブルーザー・ブロディとの超獣コンビで参加を果たすと、優勝の栄冠こそはザ・ファンクスに譲ったものの(ブロディの反則負け)、試合内容では終始圧倒。
翌年4月、大阪府立体育館(現在のエディオンアリーナ大阪)で行われたシングルマッチでは、ハンセンがテリーの首にブルロープを巻き付けて場外を引きずり回し、揚げ句にはチアガール姿のテリー応援団の悲鳴が上がる中、エプロンから絞首刑状態で吊り下げて完全失神にまで追い込んでみせた(ドリーが止めに入ってハンセンの反則勝ち)。
引退戦となった’83年8月のタッグマッチも、結果こそはテリーがハンセンのパートナーを務めたテリー・ゴディに、トップロープからの回転エビ固めを決めて勝利したが、テリーのボロボロ状態からして、ハンセンとの地力の差は歴然としていた(ちなみにテリーは1年後、現役復帰)。
その後、全日においてはハンセンを中心とした新勢力が台頭し、ファンクスのみならず旧世代のレジェンド外国人レスラーたちの活躍は、めっきり減っていくことになる。
外国人陣営とはいえ、日本のマット界で初ともいえる完全世代交代をハンセンは実現したわけで、その意味からも「テキサスの化石になれ!」は歴史的名セリフと言えるだろう。
スタン・ハンセン
***************************************
PROFILE●1949年8月29日生まれ。米国テキサス州出身。身長195㎝、体重140㎏。得意技/ウエスタン・ラリアット、エルボー・ドロップ。
文・脇本深八