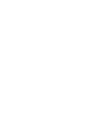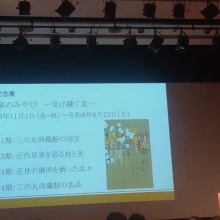「徳勝龍と聞いて、四股名の画数が多いなというぐらいで、ピンとくるファンは少なかったんじゃないでしょうか。この2年、ほとんど十両暮らし。三役経験も、三賞をもらったことすらなく、相撲っぷりも地味。“不細工な相撲取り”と自称し、仲間の担当記者でも話したことのある人はあまりいませんでしたから。NHK解説者の北の富士さんも、千秋楽の優勝インタビューを聞いて、『へえ、初めて声を聞いたけど、こんなに明るいヤツだったんだ』と言ってましたからね」(担当記者)
それがなぜ、突然何かに取り付かれたように快進撃を見せたのか。それは、7日目の朝、大阪から上京していた恩師の伊東勝人・近畿大学相撲部監督が急死したことが大きい。
近大時代、ビッグタイトルとは無縁だった徳勝龍は、伊東監督に背中を押される形で木瀬部屋に入門。その恩を忘れないため、四股名の「勝」という字は伊東監督の名前から取った。それだけに、亡くなったときのショックは大変なものだった。
「自分には相撲しかないので、いい相撲を取るしか(恩返しは)ない」
そう話した翌日から、明らかに流れが変わった。8日目から14日目までの7日間中6番、10日目からは5番連続で攻め込まれ、土俵際に詰まってからの突き落としで逆転勝ちしている。
14日目の正代との1敗対決を制したのも、この突き落としだった。最後まで勝負を諦めなかった証拠だ。それ以上に驚いたのは、千秋楽の「史上最大の格差対決」といわれた大関・貴景勝戦だった。一転して真っ向勝負を挑んで左四つで堂々と寄り切り、奈良県出身では98年ぶりとなる優勝を自力でもぎ取った。
「自分なんかが優勝していいんでしょうか。意識することなく…ウソです。メッチャ意識していましたよ」
優勝インタビューでは関西人ならではのノリで会場を沸かせた徳勝龍。ここまで出し抜かれると“番付不信病”になるファンも続出しそうだ。